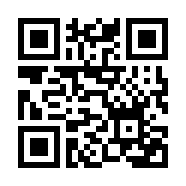
目次
序文 10年以内に過半数の会社が65歳定年制になる
前編 「65歳定年」と「企業型確定拠出年金」の導入 執筆者 北見昌朗
第1部 65歳定年制の導入に伴う給与の見直し方
その① 民間企業における定年は「60歳」が大半
その② 基本給を見直しながら「評価手当」を新設へ
その③ 既存の60代の給与の移行方法は? 新給与が従前よりも高いケース
その④ 既存の60代の給与の移行方法は? 新給与が従前よりも低いケース
その⑤ 60代の給与相場
その⑥ 筆者が独自で行っている給与調査
その⑦ 無料の賃金診断を受けるには
その⑧ 先例となった公務員の65歳定年制の内容
第2部 65歳定年制の導入に伴う退職金の見直し方
その① 退職金は不利益変更だと言われないように配慮を
その② 60歳で退職金をもらっても退職金控除を受けられる
その③ 中小企業退職金共済は60歳以降に掛け金を停止できる
第3部 確定拠出年金制度の導入
その① 企業型DCとは
その② 65歳定年制だから安心して掛けやすくなる
その③ 会社側のメリット・デメリット
その④ 掛け金の掛け方
その⑤ 企業型DCを導入した場合の給与明細の作り方
その⑥ 「望ましくないパターン」退職一時金制度を廃止して企業型DCを導入へ
その⑦ 「望ましいパターン」退職一時金制度を存続してほかに企業型DCを導入へ
その⑧ 用語解説 「退職一時金」と「退職年金」とは
その⑨ 用語解説 「確定拠出年金」と「確定給付年金」とは
その⑩ 用語解説 中小企業退職金共済・特定退職金共済とは
その⑪ 企業型DCと中小企業退職金共済とを比較すると
第4部 社員に対する説明の仕方
その① 65歳定年制の導入に伴う給与・退職金の見直し方
この「社員に対する説明」は、著者が開設した特設サイトでダウンロード可能
その② 公的年金制度に関する社員研修会
その③ 企業型DCを導入する
その④ いわゆる「2000万円問題」
第5部 金融機関が普及に努める企業型DCの導入費用
後編 60歳以降の給与減額に関する法律論 執筆者 北見拓也
論点① 65歳定年制を導入し、60歳を機に賃金を引き下げることができるか?
就業規則の変更時期が改正法が施行された後なので「違法」となったケース
裁判例① (賃金の引き下げを違法と判断した事例)
裁判例② (賃金の引き下げを違法と判断した事例)
就業規則の変更時期が改正法が施行された直後だったので「適法」となったケース
裁判例③ (賃金の引き下げを適法と判断した事例)
賃金減額の是非は既得の地位、権利を奪うものとなるかで判断
ケース① 継続雇用制度を導入済みのところは不利益変更と評価されない
ケース② 既に65歳定年制を採用しているところでは不利益変更に
ケース③ 事実上「定年」がなかったところは不利益変更の可能性も
ケース④ 賃金が下がる場合には本人同意が必要
論点② 退職金の支払い時期を60歳から65歳へ遅らせることができるか?
その① 退職金の支払いが遅くなるのは不利益変更
その② 65歳定年制になっても退職金の支払い時期の遅れは合理性なし
その③ 退職金の金額を上乗せなど不利益緩和措置が必要
著者の略歴
